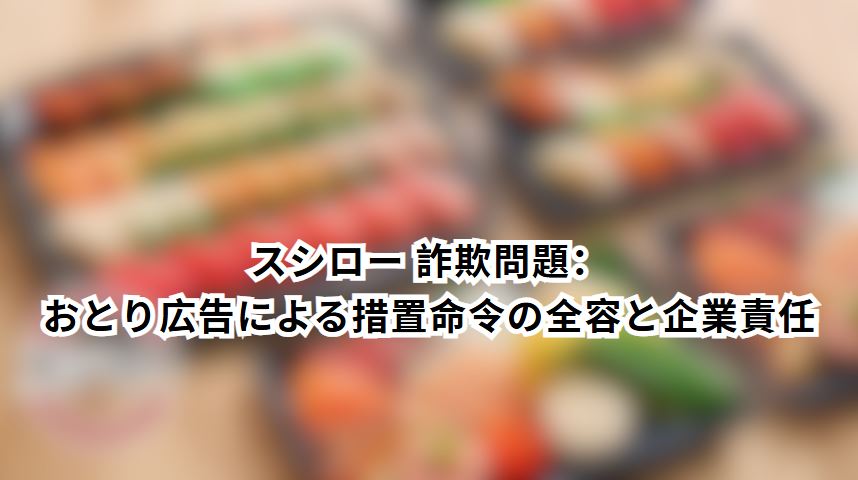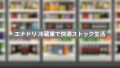はじめに
日本全国に600店舗以上を展開する大手回転寿司チェーン「スシロー」が、2022年に「おとり広告」に該当する表示を行っていたとして、消費者庁から景品表示法違反に基づく措置命令を受けました。この一件は、飲食業界全体に大きな波紋を呼び、 スシロー 詐欺 というワードがSNSやニュースメディアで広く拡散されることになりました。
本記事では、行政が指摘した不当表示の具体的内容と、それに対するスシロー側の対応、企業責任の観点から見た課題と今後の展望について詳しく解説します。
問題の概要:何が「詐欺」とされたのか?
スシローに対する批判の発端は、広告に掲載された寿司メニューが実際にはほとんどの店舗で提供されなかったという点にあります。2021年から2022年にかけて、以下のようなキャンペーンが行われました:
- 「新物!濃厚うに包み 100円」(2021年9月〜10月)
- 「うに三種盛り」(同上)
- 「豪華かにづくし」(2021年11月〜12月)
これらのメニューはテレビCMやチラシ、公式サイトなどを通じて広く宣伝されました。しかし、実際には全国のスシロー店舗のうち、500店舗以上が初日から欠品、またはまったく提供されていない状況に陥っていたことが判明しています。
このような状態にもかかわらず、スシローは「売切御免」としながらも広告の掲載を継続。消費者庁はこれを「おとり広告」による不当表示と判断し、2022年6月9日、運営元である株式会社あきんどスシローに対し景品表示法第5条第3号に基づく措置命令 を下しました。
景品表示法における「おとり広告」とは?
景品表示法では、実際には販売する意思や能力がない商品について、あたかも販売できるかのように表示する行為を「おとり広告」として禁止しています。
今回のスシローのケースでは:
- 宣伝初日から在庫切れ状態の店舗が多数
- 「売切れ御免」と表示していたが、入荷の目処すら立っていない状況
- 宣伝を中止せず広告を継続
という実態が、景品表示法違反にあたると認定されました。
消費者庁による措置命令の内容
消費者庁が発表した措置命令では、スシローに対して以下の対応を求めています:
- 不当表示の再発防止措置
- 役職員に対する表示ルールの教育徹底
- 一般消費者への周知(お詫びや説明)
- 広告表示の見直し
処分自体には罰金刑や営業停止などの刑事罰は含まれていませんが、企業の信頼を大きく損なう深刻な行政指導であることは間違いありません。
元従業員の証言と現場の実態
一部のメディア取材によれば、スシローの元従業員は「初日から全く提供されない商品があった」と証言しており、物流・供給体制の不備が構造的なものであった可能性も指摘されています。
このような現場の声からは、広告と実際の販売体制との間に乖離があり、内部の調整不足が広告戦略を上回っていたことが伺えます。
企業側の対応と反省
措置命令を受けたスシローは、公式に「真摯に受け止め、再発防止に努める」との声明を発表しました。2022年以降、広告表示の方法や販売開始前の在庫調整体制に見直しが行われたとされています。
また、役員・現場スタッフ向けに景品表示法の研修を実施するなど、企業としてのコンプライアンス強化策も打ち出しています。
業界と消費者への影響
この一件は、単なるスシロー単独の問題にとどまりません。消費者の信頼を得るためには、商品を「見せる」広告と、「提供する」現場との整合性が不可欠であるという教訓を、飲食・小売業界全体に突きつけたのです。
特に「限定商品」や「先着○名」などの販売戦略をとる企業にとって、在庫・供給体制の不備は企業価値そのものを毀損するリスクに直結します。
再発防止への展望と課題
今後スシローが再発防止に向けて真に取り組むべき課題は以下の通りです:
- 広告責任者と現場の連携強化
- 在庫と販売予測の精度向上
- 正確かつタイムリーな情報開示
- クレーム・苦情対応体制の強化
また、消費者側も過度な期待に流されず、「実際に提供されるかどうか」の確認を行うなど、企業と消費者の健全な関係づくりが求められます。
まとめ:スシロー「詐欺」問題が投げかけたもの
| 項目 | 内容 |
| 問題の本質 | 広告で宣伝した商品の多くが提供不能であった点 |
| 行政判断 | 景品表示法違反(おとり広告)として措置命令 |
| 企業の対応 | 表示の見直し、内部教育、供給体制の強化 |
| 消費者への影響 | 信頼低下、炎上、ブランドイメージ毀損 |
| 今後の展望 | 広告と現場運用の整合性を高める仕組みづくり |
スシローの「詐欺」とも言われたおとり広告問題は、一企業の過ちというよりも、現代マーケティングと供給体制のギャップが引き起こした必然とも言えるでしょう。企業は誠実な広告表示と正確な在庫管理を通じて、失った信頼を少しずつ取り戻す努力が求められています。